
2025/05/11
循環がつくる未来──牧場で見つけた境界線のない豊かさ
神戸の閑静な住宅街のすぐそば。まるでタイムリープしたかのように突如目の前に現れるのが弓削牧場です。
都会にほど近いこの場所に木のぬくもりを感じるレストランがあり、絶品のチーズをふんだんに使った愛あるお料理が頂けます。ここでは自分自身が自然と調和していくような温かな雰囲気があります。牧場の開始当初から当時は珍しかった牛の放牧を取り入れ、牛乳の廃棄を防ぐためにチーズづくりをスタート。

常にご自身の半径5mにある自然、動物、そして世代を問わず家族や仲間を大切に循環されてきた弓削牧場の和子さんと次女の麻子さんにお話を伺いました。
「農業を守り続ける」熱い想いで始まったチーズづくり

和子さん:初代は主人の父、吉道が脱サラで農業を始め、ここからほど近い箕谷の山で牛を飼い始めました。都市開発が進み、1970年に今の場所に移りましたが、当時から午前は牛を放牧するのどかな酪農家でしたね。朝の5時の作業が終わって、7時から山に放牧。牛たちは山を駆け上がっていくんです。そしてちょうど12時頃にわっと降りてくる。そこからは牛舎に入れて、夕方5時の搾乳を待つという半日放牧をしていました。
麻子さん:私はおじいちゃんが亡くなったあとに生まれたので会ったことはないんです。おじいちゃんは大阪の北浜に「ブラジレイロ」という喫茶店を開いていて、朝に搾った牛乳をもってカフェラテを淹れていたんです。足踏み式のオルガンを弾きながら孫と踊るハイカラおじいちゃんだったそうです。
── めちゃくちゃオシャレなおじいさまですね!当時、放牧というのは珍しかったのですか?
和子さん:はい、都市近郊の牧場で放牧できるのはうちぐらいしかなかったですね。その後、初代が亡くなり、主人があとを継ぎました。これからどうやってこの牧場を守るのか、農業、一次産業を守るのかと考えたとき、「カマンベールチーズを作りたい」と思い立ち、そこからチーズの歴史が始まりました。
── なぜチーズを始めようと思われたのですか?
和子さん:市場に合わせて生産量を調整する時代だったのでせっかく絞った牛乳を廃棄せざるを得ないときがあったんです。廃棄せず、循環するにはどうすれば良いかと考えた結果、カマンベールチーズを作ろうとなったわけです。
しかし、当時は知識も資料もありませんでした。アメリカのTHE BOOK OF CHEESEという50年前のチーズ作りの文献を、夜な夜な解体新書のように訳しながら、失敗しながら学習する日々でした。当時の農水省にも直接電話をして、相談を持ちかけたところ、ナチュラルチーズの需要開発事業が立ち上がり、補助を受けながら開発を続けました。

── それが今の弓削牧場につながっているのですね。
和子さん:
そして自分たちで一生懸命作ったチーズの食べ方の発信をしたいと考え、その拠点として三角屋根のチーズハウスを作りました。農家が自分たちで販売・発信拠点を持つことも当時は全国で例がなかったんです。今で言う6次産業化ですね。そこから、レストランを始めたり、牧場ウェディングをしたり、ライブやカルチャースクールをしたり、様々な形で発展していきました。
牧場は仕事場ではなく、我が家

── 現在はマークにもなっている3人のお子さんも一緒に経営しているんですね。
麻子さん:兄はチーズ作りと牛飼いと経理、姉は現在、アメリカのポートランドにいて、オンラインショップなどの担当をしています。私はレストランや催事の担当です。今まで父母が2人でやってきたことを私たち兄弟でできるかという模索中です。でも、家はここなので、朝は毎朝父母も早く起きて来ますし、仕事というよりもここで生きているという感覚です。
── ご主人や和子さんが動けるうちから権限委譲されているのは特徴的だと思います。麻子さんには当然継ぐだろうという感覚はあったのでしょうか?
麻子さん:よく「なぜ継ごうと思ったのですか」と聞かれるのですが、私は継ごうと思ったことはないんです。ここで父と母を手伝うのが私の普通だったから。ここは家なんですよ。自分の家がなくなるのは嫌だから、自分は手伝うみたいなイメージ。むしろ「継いでね」って言われてたら、反発して継がなかったかもしれません。ここで父と母が一生懸命チーズ作りをしている姿を見ているので、私も一緒にやろうという感覚です。
和子さん:当時は家族、スタッフ含めて最大で13名で食事しながらミーティングしていました。子どもはほったらかし。なんでそんなに一生懸命やっているのかな?と思っていたかもしれないですね。
麻子さん:学校から帰ったらチーズ工房に母がいて、牛舎に父がいる。レストランに西村という母と一緒の世代の女性がいて、彼女が厨房にいる。帰ったら3人のとこ行って、厨房でおやつ食べさせてもらって、牛舎で父が牛に乗せてくれて…そんな中で私は育ちました。
── たくさんの分断がある社会の中で、世代もごちゃまぜ、家と暮らし、仕事もグッとつながっていてとても豊かに聞こえますね。和子さんたちの姿を見て一緒にやりたいと思ったんですよね。
和子さん:私がこの牧場に来たとき、ここは可能性に満ち溢れている、キャンバスだと思いましたね。
廃棄はゼロ。もったいない精神で叶えた循環の連鎖
麻子さん:父と母は現在、バイオガスのエネルギーを作る方がホットトピックなんですよ。
※バイオガスとは
バイオ燃料の一種で、生物の排泄物、有機質肥料、生分解性物質、汚泥、汚水、ゴミ、エネルギー作物などの発酵、嫌気性消化により発生するガスのこと。(出典:Wikipedia)
和子さん:バイオガス導入のきっかけは、ご近所からのクレームでした。都市化が進み、裏の山が削られ、住宅街になったんです。すると、風の流れが変わったのか、牛の匂いが住宅街に流れ出てしまい、クレームが入りました。私たちはご迷惑をおかけするために牛を飼っているわけではないので、なにか対策ができないかと調べたところ、牛のふん尿からバイオガスが作れると知りました。帯広畜産大学の梅津教授が当時の第一人者なので、直接電話を入れて相談したのが始まりです。
── チーズの始まりと同様に直接アタックですね!
和子さん:しかし、当時はまだ大型化されておらず、検討を重ねましたが、導入に2億〜3億かかると言われました。本当に悔しい思いをして、小さくても自分たちでやってみようとチャレンジした結果、バイオガスを発生させることができました。それがきっかけで帯広畜産大学と神戸大学とも連携することになり、実証実験を重ね、ミニバイオガスユニットができてきました。
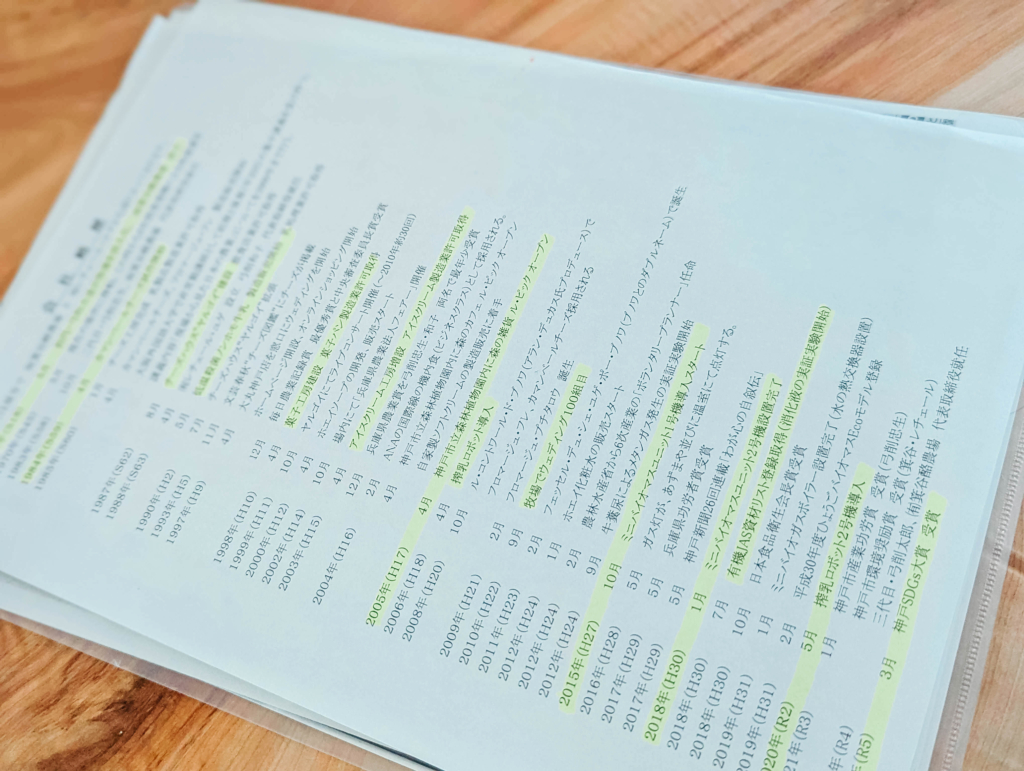
──ここから牧場内でのエネルギー循環が始まったんですね。
麻子さん:弓削牧場は牛の頭数が限られているため、バイオガスユニットのボイラーを温めるために、牛のふん尿だけでなく、間伐材を薪にして燃やす作業も毎日行われています。これが山の管理にもつながっているんです。
和子さん:さらにバイオガスを取ったあとの副産物として液肥ができるんです。これが有機JAS資材認証が取れました。元々、牧場の中ではすでに農薬とか化学肥料はほとんど使ってなかったんですが、それ以降はすべてを堆肥と液肥だけで野菜を育てるようにしています。
この液肥の価値に気づいたのがお米の栽培です。主人と立ち上げたNPO都市型農業を考える会の副理事長である中西重嬉さんに「すべて買い取るので、液肥だけでお米を作ってほしい」と依頼しました。すると、通常、有機でお米を育てると一反300キロほどらしいのですが、結果的に420キロのお米ができ、味も美味しいと評判になったんです。

── 循環の意識がとても高いと思ったのですが、なぜなのでしょうか?
和子さん:今日はホエイシチューを召し上がりましたか?
初代のおじいちゃんがいた頃の食卓には、クリスマスには鶏の丸焼きをつくったり、テールスープをつくったり、外国のお料理がたくさんありました。実はおじいちゃんが生きていた頃、私がシチューを作っていると後ろで「ホエイを入れろ」と後ろでいつも呟いていたんです。当時は聞き流してしまっていたんですが、レストランができたとき、ホエイシチューこそがここでしか出せない弓削の食文化だと気づいたんです。ホエイはチーズの副産物ですが、シチューや石けんづくりに活用しているので廃棄はほぼないんです。すべて循環しています。

※ホエイとは
乳清(にゅうせい)。牛乳から乳脂肪分やカゼインなどを除いた水溶液。(出典:Wikipedia)
麻子さん:おじいさんは戦後の時代だったこともあり、もったいない精神があったんです。どんなものでも大事に使うことを意識していました。おじいちゃんのその精神が父に受け継がれているんでしょうね。
農と若者をつなぐ場作り

── バイオガスなど時代に先駆けた取り組みをされてきていますね。
和子さん:私が個人的にこれから広まってほしいと思っているのは半農半Xです。これから、5年、10年先の若者の食をどうするのかということが気になっています。今、作り手がどんどんいなくなっています。これからは農業以外で収益を得つつ、農業に興味ある人が取り組める施策を増やしてほしいです。自分で種をまいて、育てる腕があれば、田舎へ入ることもできると思うんです。今の70代のおじいさん、おばあさんたちがいなくなったら、みんな食べものをどうするのだろうというのが一番の心配なんです。次の世代につなぐためにどうつなげるのか、模索を続けています。
(インタビューはここまで)


弓削牧場のシンボルである3人の子どものマークは、和子さんご自身で描かれたものだそうです。家族や農業への想いは、初代・吉道さんの時代から子どもたちの麻子さんやお孫さんたちへと自然に受け継がれていることが、お話から伝わってきました。今、「弓削牧場のファミリー」という温かなつながりは、家族だけでなく、若い世代にも届き始めています。牧場の言葉にふれた若者たちは、きっと農業の未来に欠かせない存在になるはずです。都市の中にあるこの小さな牧場には、今も無限のキャンパスが広がっています。
ライター/なかあづさ
そんな弓削牧場さんとチーズめでたべ会を開催!

aiyueyoでは今日ご紹介した弓削牧場さんがつくる優しくおいしいチーズたちを味わうイベントを開催します。オンラインでご自宅と弓削牧場を接続。直接作り手の声を浴びながらおいしいチーズをお楽しみくだい。
お申し込みは本日の21時まで!ピンときたはぜひお申し込みくださいね。詳細はこちら
INFORMATION




-1024x529.png)

